第3回 漫画から哲学、経済学まで—幅広い読書経験が人工知能研究の土台となった—
今回は武蔵大学社会学部メディア社会学科の庄司昌彦教授と宇田川敦史准教授が、武蔵中学・高校の卒業生でもある、東京大学次世代知能科学研究センターの松原仁教授(本学園データサイエンス研究所アドバイザリーボード)に、人工知能研究の足場となった人文知との出会いや近年の研究活動などについてお話をうかがいました。
プロフィール
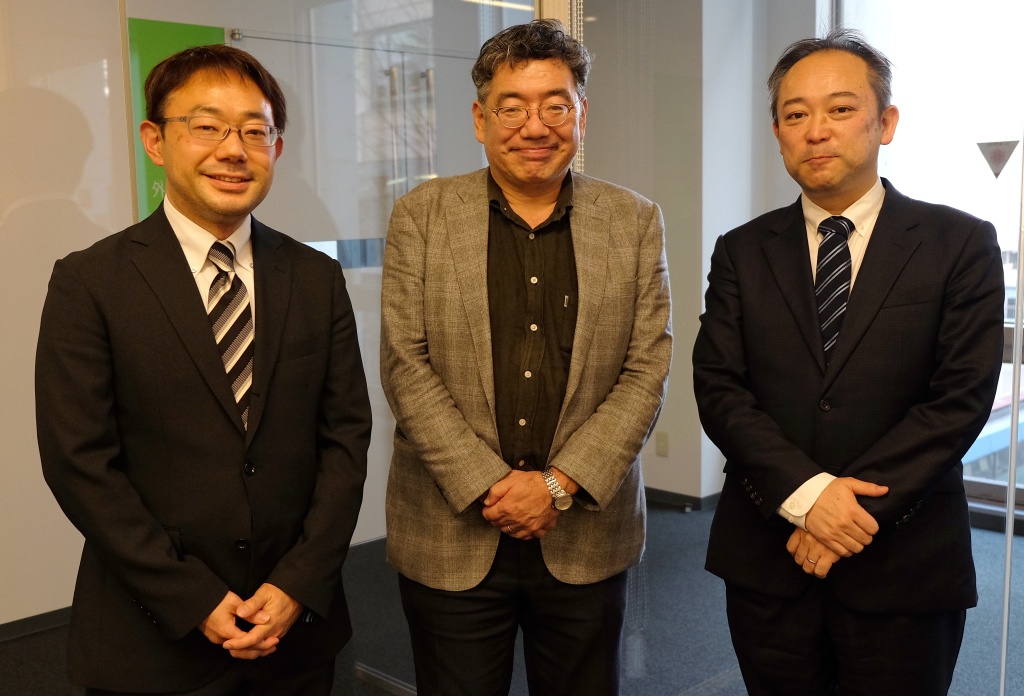
中央:松原仁(まつばらひとし)
東京大学次世代知能科学研究センター教授。
1959年東京生まれ。1981年、東京大学理学部情報科学科卒業。1986年、同大学大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了(工学博士)。同年電子技術総合研究所(現 産業技術総合研究所)入所。2000年公立はこだて未来大学システム情報科学部教授。2020年より現職。専門は人工知能(AI)。元人工知能学会会長。著書に『鉄腕アトムは実現できるか』『先を読む頭脳』『AIに心は宿るのか』など。
1959年東京生まれ。1981年、東京大学理学部情報科学科卒業。1986年、同大学大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了(工学博士)。同年電子技術総合研究所(現 産業技術総合研究所)入所。2000年公立はこだて未来大学システム情報科学部教授。2020年より現職。専門は人工知能(AI)。元人工知能学会会長。著書に『鉄腕アトムは実現できるか』『先を読む頭脳』『AIに心は宿るのか』など。
右:庄司昌彦(しょうじまさひこ)
武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。
1976年東京都生まれ。2002年、中央大学大学院総合政策研究科博士前期課程修了。修士(総合政策)。2002年、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員。2015年、同准教授・主任研究員。2018年、同准教授・主幹研究員を経て、2019年4月より現職。デジタル庁オープンデータ伝道師、デジタル庁「データ戦略推進WG」構成員も務めている。近著に『入門メディア社会学』(分担執筆)。
1976年東京都生まれ。2002年、中央大学大学院総合政策研究科博士前期課程修了。修士(総合政策)。2002年、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員。2015年、同准教授・主任研究員。2018年、同准教授・主幹研究員を経て、2019年4月より現職。デジタル庁オープンデータ伝道師、デジタル庁「データ戦略推進WG」構成員も務めている。近著に『入門メディア社会学』(分担執筆)。
左:宇田川敦史(うだがわあつし)
武蔵大学社会学部メディア社会学科准教授。
1977年東京都生まれ。2001年、京都大学総合人間学部基礎科学科人間情報論専攻卒業。同年日本IBM株式会社入社。2009年、楽天株式会社入社。2018年、東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。修士(学際情報学)。2022年4月より現職。著書に『ソーシャルメディア・スタディーズ』(分担執筆)。
1977年東京都生まれ。2001年、京都大学総合人間学部基礎科学科人間情報論専攻卒業。同年日本IBM株式会社入社。2009年、楽天株式会社入社。2018年、東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。修士(学際情報学)。2022年4月より現職。著書に『ソーシャルメディア・スタディーズ』(分担執筆)。
武蔵中学・高校で培った読書習慣が知の深淵へと誘った
庄司教授(以下、庄司):松原先生は少年時代に『鉄腕アトム』の天馬先生に憧れていたと伺いました。これまでのキャリア形成や研究において影響を受けた本などについてご紹介をいただければと思います。
松原教授(以下、松原):幼稚園の時にアニメの『鉄腕アトム』を見ていました。アニメの方は子ども向けということもあり、原作と比較するとかなりシンプルな勧善懲悪のストーリーになっています。小学生になってからコミック版を読むようになったところ、鉄腕アトムがかなり深い物語だということが分かってきました。例えば僕が一番好きなシーンに「人が美しいというのがロボットの僕にはわからない」とアトムが悩みながら言う場面がありますが、これは「機械に心はあるのか」という問いにもつながるエピソードです。何かを美しいと人間が思うということを知識としてはアトムも知っていますが、心から美しいと人間が言う時の気持ちが分からない。AIという言葉も知らない子どもの頃のことですが、今にして思うとそのシーンの記憶がずっと頭の片隅にあったように思います。
宇田川准教授(以下、宇田川):武蔵中学・高校ではフロイトを読むような教育や環境があったのでしょうか?
松原:フロイトに限らず読書をする風潮はありました。中学生の頃から少し背伸びをして、難しい哲学書を読んだりはしましたね。武蔵中学・高校は大学っぽいところのある学校で、背伸びしてでも原典を読まないといけないという風潮がありました。ですから僕がフロイトに夢中になったのは、おそらくその中でどなたか先生がフロイトに触れたので面白そうだと思って読んだのがきっかけだと思います。高校時代は他にもマルクスの経済学やデカルトの心身二元論なども読みました。大学に入って情報科学科に進んでからはコンピュータの専門書を読むようになりましたが、人文系の本を読む習慣は続いていました。ところが理系に進学した学生は人文書を嫌う傾向があるため読書に関しては大学の友人とあまり話が合いませんでした。幅広い読書習慣がついたことに関しては武蔵中学・高校時代の先生方に感謝すべきかもしれません。
宇田川:武蔵では、読書の結果を何かしらの形でアウトプットする場はあったのでしょうか?
松原:場合によってはありました。他の生徒の前で発表した記憶もありますし、大学の研究室を訪ねるのと同じ感覚で先生の部屋に遊びに行って本の感想の話し相手になっていただいたこともあります。「この間勧めた本、お前読んで分かったか?」「いいポイント突いてるけれど、まだちょっと浅いな」とか言われて。
庄司:情報学を専攻してから自然言語への関心を深める方もいらっしゃいますが、先生の場合はもともと人文系の素地がおありだったのですね。
松原:そうですね。やはり知能とは何かを知りたいという好奇心や、アトムを作りたいという抽象的な関心が人工知能研究に携わる足がかりになったのだと思います。具体的な領域としては自然言語処理や画像認識を大学や大学院で学びましたが、そういうことをAIにやらせたいという関心の持ち方をしたのではなく、知能とは何か、無意識とは何なのかという哲学的な議論の方に関心が向いていました。
40年近く前の東大には情報科学科はあったものの、まだAIの授業はありませんでした。そこでAIUEOという自主ゼミのような学生だけの組織に入って、先輩とAIの論文を交代で読んだり春休みや夏休みに合宿をしながら、それこそ知能とは何かという哲学的な議論を重ねました。そこで、将来的に鉄腕アトムのようなロボットは作れるのかという話をお酒飲みながら夜を徹して議論をしていたのが、今思うといい経験になっていたと思います。
その後、寺子屋という勉強会をある出版社の人が作ってくれたのですが、そこは哲学者とAI研究者が議論をする場で、2カ月に1度くらいの頻度で若手AI研究者として僕も入れてもらっていました。そこには言語哲学者の土屋俊などもいました、例えば「AIは知能を持てるのか」という問いについては、哲学者は哲学者で理屈があります。それを聞いて侃々諤々とした議論が始まるわけですが、そういう場に縁があったのも、哲学への関心の延長からAIの研究を始めたからだと思います。
松原教授(以下、松原):幼稚園の時にアニメの『鉄腕アトム』を見ていました。アニメの方は子ども向けということもあり、原作と比較するとかなりシンプルな勧善懲悪のストーリーになっています。小学生になってからコミック版を読むようになったところ、鉄腕アトムがかなり深い物語だということが分かってきました。例えば僕が一番好きなシーンに「人が美しいというのがロボットの僕にはわからない」とアトムが悩みながら言う場面がありますが、これは「機械に心はあるのか」という問いにもつながるエピソードです。何かを美しいと人間が思うということを知識としてはアトムも知っていますが、心から美しいと人間が言う時の気持ちが分からない。AIという言葉も知らない子どもの頃のことですが、今にして思うとそのシーンの記憶がずっと頭の片隅にあったように思います。
日本には鉄腕アトムが好きでロボット研究者になった人がたくさんいます。僕もそのままいくとロボット研究者になっていそうなものですが、結果的にAI研究者になりました。ではなぜAI研究に関心が向いたのかというと、中学生の時にフロイトに関心を持ったことがきっかけです。当時の僕が本当にフロイトを理解できていたかは分かりませんが、今のように分かりやすい解説本もない時代でしたから、フロイトの『精神分析入門』などを読んでいました。
僕が感動したのは、無意識が人間の心を動かしている原動力になっていて、それはなかなか表に出てこない、本人も分かっていないことが多いということでした。そのくだりを読んで「そうか、自分が思ってもみないようなことをしたくなる時があるのは、そういう理由だったのだ」と中学生なりに腑に落ちたのです。そして心についてもっと知りたいと思うようになりました。そうしたことと、鉄腕アトム好きというのが、何となく合致していくうちに理科系の大学に進学して、AIという研究分野があると知った時に「自分がやりたかったのは、もしかするとこの分野なのかもしれない」ということでAI研究の道に進みました。
宇田川准教授(以下、宇田川):武蔵中学・高校ではフロイトを読むような教育や環境があったのでしょうか?
宇田川:武蔵では、読書の結果を何かしらの形でアウトプットする場はあったのでしょうか?
松原:場合によってはありました。他の生徒の前で発表した記憶もありますし、大学の研究室を訪ねるのと同じ感覚で先生の部屋に遊びに行って本の感想の話し相手になっていただいたこともあります。「この間勧めた本、お前読んで分かったか?」「いいポイント突いてるけれど、まだちょっと浅いな」とか言われて。
庄司:情報学を専攻してから自然言語への関心を深める方もいらっしゃいますが、先生の場合はもともと人文系の素地がおありだったのですね。
松原:そうですね。やはり知能とは何かを知りたいという好奇心や、アトムを作りたいという抽象的な関心が人工知能研究に携わる足がかりになったのだと思います。具体的な領域としては自然言語処理や画像認識を大学や大学院で学びましたが、そういうことをAIにやらせたいという関心の持ち方をしたのではなく、知能とは何か、無意識とは何なのかという哲学的な議論の方に関心が向いていました。
40年近く前の東大には情報科学科はあったものの、まだAIの授業はありませんでした。そこでAIUEOという自主ゼミのような学生だけの組織に入って、先輩とAIの論文を交代で読んだり春休みや夏休みに合宿をしながら、それこそ知能とは何かという哲学的な議論を重ねました。そこで、将来的に鉄腕アトムのようなロボットは作れるのかという話をお酒飲みながら夜を徹して議論をしていたのが、今思うといい経験になっていたと思います。
その後、寺子屋という勉強会をある出版社の人が作ってくれたのですが、そこは哲学者とAI研究者が議論をする場で、2カ月に1度くらいの頻度で若手AI研究者として僕も入れてもらっていました。そこには言語哲学者の土屋俊などもいました、例えば「AIは知能を持てるのか」という問いについては、哲学者は哲学者で理屈があります。それを聞いて侃々諤々とした議論が始まるわけですが、そういう場に縁があったのも、哲学への関心の延長からAIの研究を始めたからだと思います。
ゲームの人工知能の研究はなぜ重要なのか?

庄司:松原先生は抽象的なご関心からAI研究に携わるようになりましたが、ロボカップや将棋AIなど目に見える形でAIを活用されてきました。それには何か意図があったのでしょうか?
松原:目指す理想は抽象的でも研究成果が世の中に伝わるように目標を設定しないと、仲間を増やせないと強く思っていたのでアウトプットを具体的にすることを意識してきました。当時はAI冬の時代だったのでなおさらです。プログラミングの技術を覚えて最初に書きはじめたのが将棋プログラムでした。当時の将棋AIはものすごく弱かったのですが、いつかは名人に勝てるとその時から思っていました。それ以降、ロボットにサッカーをさせるロボカップや小説を書かせるAI「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」など、分かりやすい目標を立てて取り組んできました。そうでないと、世の中の多くの人に理解してもらえず、結局AIが一部の人たちの知的好奇心を満たすためだけの研究になってしまうからです。実際に人工知能研究の黎明期はそういう所がありましたから、そこから脱却するべきだと強く思っていました。
宇田川:汎用AIをいきなり作ろうとするよりは、構成的なアプローチで1個ずつ積み上げるやり方の方が良いという発想ですね。
松原:はい、汎用AIを最終目標としても、いきなり最初から「汎用AIを作ろう」とだけ言ってしまうと、何をやって良いか分からないじゃないですか。実現できるまで何十年もかかりますし、その間は何も目に見える成果を世の中に発信できなくなってしまいます。ですから、たとえば将棋AIが名人に勝ったり、最近のようにChatGPTが発表されたりと、時々エポックメイキングな技術を実現しながら少しずつ成果を積み上げていくことが大切だと思います。
宇田川:その中でも最初に将棋AIに挑戦したのはなぜでしょうか。
松原:欧米のAI研究が活発になったきっかけのひとつがチェスでした。アラン・チューリングとクロード・シャノンが1940年代終盤に知性の例としてチェスを出しています。欧米において、チェスの強さは頭の良さの象徴でした。そこでコンピュータにもチェスをさせようとしました。
例えば想定される損害を最小化させる探索方法であるミニマックス法を使えば対戦時に次の手を出せるとチューリングとシャノンが言ったことから、ジョン・マッカーシーなどの研究者たちがチェスのプログラムを書き始めるようになりました。最終的にはIBMのスーパーコンピュータ「ディープ・ブルー」がチェスの世界チャンピオンのガルリ・カスパロフを打ち負かしますが、そのようにしてAI研究のメインストリームをチェスAIが走ってきたわけです。
ところが日本で僕がAI研究を始めようとした頃は、ゲームAIを研究するなどもってのほかとされました。実際に僕も色々な人からそんな研究はやめろと忠告されましたし、なかには「そんな研究をする君は人間のクズだ」と面と向かって言われたこともあります。
僕がゲームAIを本格的に研究しようと思った時期は第2次AIブームが下火になり、日本のAI研究も縮小されていった時期と重なっていました。しかしゲームAIの研究をしてはいけないという風潮自体が、日本のAI研究を後退させかねないと考えていたので、それに対抗して将棋のAIの研究に取り組んだ所はあります。
自然言語処理は、AI研究が下火になっている中でも「日本語と英語の翻訳ができると日本人にとってメリットがある」と目標を掲げれば多くの人にとって説得力を持つので、企業としても出資をしやすかった。ところが将棋となると「遊びに出資はできない」と言われてしまいます。アメリカだとIBMが日本円にして100億円くらいはチェスAIに投資していると思いますが、日本の電機メーカーは株主に何を言われるか分からないとか、ゲームに関心がないと言って及び腰でした。それなら自分でやりましょうということで始めたのです。
庄司:ゲームの人工知能を研究したことは限られた条件やルールの中で最もいい手を探す知能を開発することにつながりますから、そういう意味でも研究する価値があったのではないでしょうか。
松原:その通りです。将棋や囲碁といった閉じた世界でルールの決まっている問題を解くのはAIにとっては比較的易しいことです。ですから、これを実現できないようでは永遠に汎用的なAIはできないと思っていました。当時は人間の棋士がどう戦っているかを、それこそ認知科学的に研究した上で、それをプログラム化する手法が主流でした。当時のコンピュータは非力だったので、全部の手を読むどころか10手先まで読むことすらできなかったので、一部の見込みの高い手だけを先に読むということになります。
見込みが高いというのは評価値が高いということですが、機械学習もない時代でしたからその評価関数も手作りです。将棋がプロよりも断然弱い我々は、強い評価関数が作れないわけですね。それを作れるようだったら私たちは将棋の名人になっています。そんな訳で当時の将棋AIは本当に弱かったですね。
宇田川:現在のAIは大量データが特徴ですが、データとロジックの関係でいうと、当時はロジックの重要性が相対的に高かったということでしょうか?
松原:当時はロジックのみでした。現在はロジックとデータを両輪としてロボットができるのは当たり前のことだという共通認識がありますし、当時もそれを分かっていなかった訳ではないのですが、技術的な制約により実現がまだできませんでした。インターネットが普及していないため十分なデータを取ってこられませんし、仮にデータを集められたとしてもコンピュータが非力だったので、データを今のように大量に処理することは不可能でした。
宇田川:ロジックのみで構築されていたAIから機械学習を導入する転機になったのはいつごろなのでしょうか?
松原:ディープラーニングが出てくる以前の時代、たとえばチェスは1997年にディープ・ブルーが、カスパロフに勝ちましたが、開発の終盤では今でいう機械学習されたデータをかなりあのプログラムは扱っていたはずです。序盤のデータベースや過去のチェスの棋譜もふくめ、20世紀の主だったチェスの対局の記録のデータが大量に入っていると言われています。今ならそれらをディープラーニングで処理するのでしょうが、当時は未処理のデータをそのまま活用していました。この局面は何年に誰と誰が対戦して、この局面では誰がどう指したかといったデータがすぐに出てきて、少なくとも判断の参考として使っていたのだと考えられています。
チェスが将棋と異なるのは駒を取られると再利用することなく単調に減っていくことです。終盤に駒の数が減って例えば6駒くらいになると、当時のコンピュータの性能でも事前に延々とコンピュータを走らせて過去データと照らし合わせながらしらみつぶしをし、この6個の配置がこうだったらこの手順でこっちが勝つといった終盤データベースを用意することができます。
これが残り3駒くらいまでになるとだいぶ作りやすいですが、1手戻ると4駒、その前は5駒と駒が増えるたびに想定される手が指数関数的に増えて複雑になっていくので、データベースを作るのが困難になります。当時はそれに関する研究論文がたくさん出ていました。そうしたことが1手また1手と可能になると、地味ではありますが人間に対しては大きなプレッシャーとなります。駒数がある程度減ると人工知能側の必勝手順が分かってしまうので、そうなる前に勝たないといけなくなるためAIが進歩するにつれ人間の選手に残された時間が減るからです。
すでに80年代終わり頃には論理探索よりもデータ活用を重視する方向に風向きが変わっていたので、チェスで人工知能が世界チャンピオンに勝てたのは、探索の精度もさることながらデータの威力が大きかったのではないかと思います。1997年は第2次人工知能ブームも終わり、冬の時代に入っていたので、そんな時にチェスで人間に勝てたというニュースはポンと1発上がった花火のようなインパクトがありました。
宇田川:第2次人工知能ブームは「エキスパートシステム」に期待が寄せられていたので、そのころからデータベースが重視されはじめたということですね。
松原:第1次人工知能ブームでは論理的な推論が研究されていました。第2次人工知能ブームのエキスパートシステムは、専門家が専門家たり得るのは重要な知識をたくさん持っているからだという考えから始まったので、データを重視する発想が第2次ブームから出てきたということだと思います。
エドワード・ファイゲンバウムという、エキスパートシステムの祖といわれているアメリカの研究者がいますが。「知識は力なり」とフランシス・ベーコンと同じ言葉を言っていました。ただ、自然への省察から帰納法を提言したベーコンの言葉とは意味が異なり、ここでは第一次人工知能ブームで研究されていた推論能力だけでは不十分だとファイゲンバウムは言っています。つまりAIのシステムが知的であるのだとすれば、それは知識ゆえなのだということです。そうしたファイゲンバウムの考えがベースにありつつも、ハードウェアの進歩に伴い膨大なデータをコンピュータが扱えるようになったことが背景として大きいと思います。仮に第1次人工知能ブームの時点で同じことに気が付いた人がいたとしても、メモリの容量の制限により実行は難しかったはずですから。
庄司:チェスと比較すると取った駒がまた使えるようになるなどゲームとしては将棋の方が相当複雑ですよね。それでも将棋AIの開発を進められたのはコンピュータの性能が追いついていたことが要因としてあったのでしょうか?
松原:そうですね。チェスAIが人間に勝ったのが1997年で、将棋AIが名人に勝ったのが2017年で20年差がありますから結構時間がかかったと思います。おっしゃるように、20年かかってしまったのは、一つは将棋の方が難しいからで10の100乗くらい場合の数が広いというのがあります。
ただ僕が考える要因としては、日本ではゲームが研究テーマとして認められない風潮があり、スポンサーとなる企業が現れなかったことが大きいと思います。チェスAIのディープ・ブルーはIBMが出資をし、囲碁AIのAlphaGoはGoogle傘下のDeepMindが開発しました。将棋AIにはそういうスポンサーがありません。2017年に佐藤天彦名人に勝ったPonanzaはパソコンを少し高性能にしただけで勝ちました。僕も2000年代に、将棋AIの出資を募るためにいくつかの企業を回ったことがありますが、けんもほろろでした。もし当時スポンサーがついていたら、将棋AIが名人に勝つのはあと4、5年は早かったと思います。
宇田川:そのような日本と米国を中心とする欧米のAIの研究環境の違いについて、今も課題として感じられていることはありますか?
松原:今はAIが国の成長戦略のトップに挙がるくらいなので、評価は上がってきたとは思います。ただ理解が追いついた時には、日本が数十年にわたる不景気のため、かけられるお金が限定的になってしまったのが残念です。第2次ブームの時の日本は世界で一番景気のいい国の一つでしたが、あの時はまだコンピュータの性能もAIの技術も十分ではなく、2回目の冬の時代が来てしまいました。もし第3次AIブームと日本の好景気のタイミングが一致していれば、今日本がAI研究の世界トップになっていたと思います。
創造性の発揮と課題解決、AI研究におけるそれぞれの難しさ

宇田川:松原先生はゲームのAIだけではなく「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」など創造的なAIの研究もされていますね。
松原:まだ将棋AIが名人に勝つ5年前ではありましたが、研究者としてはAIが勝つのは時間の問題だと判断していたので、2012年頃から小説を書くAIの研究を始めました。これは将棋AIの研究に取り組んだ理由でもありますが、僕はみんながAI研究の中でも着手していないことをやりたがるという天邪鬼な所があるので、どこから手を付けたらいいか分からないと敬遠されがちな創造性の分野を開拓しようと思ったのです。
俳句AIは川村秀憲さんたちが「AI一茶くん」を開発しましたが、俳句に限らずAIで詩を生成すること全般が難解で、とりわけ散文がとても難しい。さらに星新一のファンだった僕が星新一の次女の星マリナさんとの知己を得て版権のあるデータに関してお力添えをいただけることになったこともありAIで小説を書くことに挑戦したいと考えました。難しい試みではありますが、目標は難易度が高い方がいいと思ったので、小説AIの研究を始めました。
宇田川:星新一は中学・高校の頃から読んでいたのでしょうか?
松原:そうです。フロイトを読んでいたのと同じ頃ですね。当時出ていた文庫本は読破していました。武蔵に通っていた頃からの友人は最近の僕に会うと「将棋にしても星新一のショートショートにしても、前から好きだったものばかりを仕事にしているよね。君の研究を見ていると趣味の延長としか思えないよ」と言われます。「いいんだよ、好きなことにしたほうが絶対やる気出るんだから」と返していますが、確かにそういうところはあります。
庄司:先生は小説家や漫画家など、いわゆる人文系やアート系の方々と一緒にお仕事をすることも多いと思いますが、それぞれの分野では暗黙知として共有されている考え方や言語から違うことも多いと思います。
松原:それについては、色々と大変なこともあります。理系の人は、同じ言葉を共有するのが難しいからと他分野の方との付き合いを敬遠する人も少なくありません。僕は話が通じないことや、言葉の使い方の違いに直面することを新鮮な刺激と捉えていますし、話し合っていくうちに、双方の言葉遣いや考え方を理解していくので、そういう所から新しいものが生まれるのではないかと考えています。
漫画家や小説家もそうですし、80年代に認知科学がブームになった頃に一緒に議論をした時も、相手は心理学者や哲学者や言語学者なので、こちらも最初は彼らが何を言っているのか全然分からなかったし、向こうも分からなかったと思います。それでも侃々諤々で議論をしていくうちに色々なアイデアが出てきて楽しかったという経験があるので、新しいテーマで最初は意思疎通が難しい人と話をするというのが好きになったのかもしれません。また、こちらとしても相手の領域について勉強したいので、「すみません、基本文献を教えてください」と伺って読んだりもします。そういう意味でも、幼少期から関心の赴くままに読書をさせてくれた親の影響と武蔵で大学並みに難解な本を多く読まされた経験から本好きになったことの影響は大きかったですね。
哲学書や専門書だけではなく、漫画も色々読んできました。当時からサンデーマガジンのような少年漫画、花とゆめなどの少女漫画も読んできて、今でも週刊漫画は読み続けています。好きなものをずっと手放さずにいると、巡り巡って研究や仕事につながることもあると思います。
庄司:先生は創造性に関わるAIだけではなく、より具体的な社会課題の解決につながるお仕事や研究もされています。創造性とはまた異なる難しさがあると思いますがいかがでしょうか?
松原:2016年7月に未来シェアというベンチャー企業を設立しました。これは函館でAIを使った公共交通システムの構築と運用を行っています。AI便乗システムと呼んでいますが、簡単にいうと乗り合いタクシーです。スマホアプリで車を呼ぶとAIが配車を決めて、同じ方向へ行く人を途中で拾って目的地に向かいます。何人も同乗すれば1人が払う費用が少なくて済みますし、Door to Doorでの移動もできます。研究開発は2000年代半ばくらいから始めて研究論文として発表できるシステムは構築できたので、その時点で一段落としてやめるか社会実装するかを議論した結果、未来シェアを創業することにしました。
今は実証実験と実運用で延べ100カ所以上で稼働しており、その領域ではトップランナーになっています。技術には自信がありましたが、事業化するにあたってはそれ以外の所での苦労がありました。例えば、交通インフラはさまざまな利害関係者が当該地域内にいて、タクシー会社だけでも何社もあります。そこでA社と仲良くするとB社との関係が悪くなるといったことなどがあるので、調整に苦労しました。
さらに、新しい公共交通システムというだけで既存の交通事業者から敵視されることもしばしばありました。もともと競合ではないので「御社の車をより有効に使うことで、御社としても収入が増えると思います」と説明すると利用してくれますが、最初は大変です。ですから、各事業者や自治体など色々な所に説明に行きました。会社を立ち上げて1、2年は本当に苦労しましたが、国交省の一部に理解されてからは交渉がスムーズに行きやすくなりました。そうして軌道に乗ってくると、他の自治体の方が見学に来て関心を持ってくれるようになります。今も資金繰りもふくめて日々の問題はたくさんありますが、それはそれですごく面白いですね、技術を社会に実装するためには技術以外のさまざまな課題を解決しなければならないことに直面できますから。
宇田川:社会学や経営学を学んできた学生たちがデータの活用の仕方を身につければ、そうした現場で広報活動や利害関係の調整などで活躍することもできそうです。
松原:未来シェアでは日本語に堪能な外国人のスタッフもいます。データ担当として、日々の膨大な乗車情報を分析してグラフにまとめて、乗り合い率の推移や曜日や時間ごとの推移、それらが地区ごとにどうなっているか、さらにそうしたデータになる背景などを分析しています。例えば、特定の曜日だけある地区の乗り合い率が高いことがデータによって明らかになった場合、そこで何が起きているのかを探ります。
宇田川:まさに「デジタルマーケティング」とよばれるような仕事ですね。
松原:そうです。この町でこの曜日に何かイベントがあるのか?などと調べていくと非常に興味深いことが分かってきます。月ごとのデータ推移を見ると、生活保護や年金支給日には明らかに乗車率が増えたりと、本当にわかりやすい。そうしたことはタクシー運転手であれば経験則として知っていることのようですが、データからもピッタリと一致します。
宇田川:そうした社会のリアルな背景までは、なかなかディープラーニングの結果を活用するだけでは分からないこともありそうですね。
松原:はい。そのように事象と事象を結びつけることができるのは、多分データを分析して解釈する人間の力だと思います。AIは分析はできても、なぜかという解釈まではできないので、そうしたスキルを身につけると、これからの社会で非常に有意な人材になると思います。
これからの時代の人文社会科学系の学生に求められるのは"AIを疑う力"

宇田川:将来的に汎用AIが実現できたとして、それを創造性の方向に使っていくのか、それとも問題解決の方向に使っていくのかは、二項対立ではないにしても、だいぶ違う研究の方向性になると思われますが、今後のAI研究はどうあるべきだとお考えですか?
松原:結論から言ってしまうと両方とも大切です。知能は創造性と課題解決の両方の側面がありますが、これまでは課題解決に関わる研究しか手を付けられてきませんでした。今後はこれまであまり手をつけられていなかった創造性に焦点を当てていくことでバランスが取れていくと思います。汎用AIを人間のような知性を持つ知能と定義するならば、それを作るためには理性だけではなく、感性の方もそれなりに持っていないと実現は難しいと思います。
宇田川:社会科学研究者の視点からすると、ChatGPTのようなツールは嘘も生成してしまいます。それがある種の創造的なエンターテインメントだと社会が割り切れるのであれば良いのですが、正しい答えを出すための問題解決ツールと捉えられてしまうと、非常に危険度が増すようにも思えるので、バランスの取り方がとても難しいと思います。
松原:ChatGPTについてはまさにおっしゃるとおりだと思います。あれは絵空事生成マシンで、たまにはまともなことを言うこともあるくらいに思っておいた方が道具としては付き合いやすいと思います。AIを神格化する動きは以前からあるので、「ChatGPTがこうおっしゃっていた」みたいな話になる可能性はかなり危険ではありますが否定できません。今でも半ばネットスラングではあるものの「Google先生」という言い方があり、Googleの検索エンジンがトップに上げた情報が真実かのように捉えられてしまうことは往々にしてあります。それと同じように「ChatGPTがこう答えたので、これは真実です」と考えられてしまうのはあり得ると思います。
宇田川:武蔵大学は人文社会科学系の大学ながらも現在積極的にデータサイエンスのプログラムを進めています。AI研究者から見てそのような場所で学ぶ学生に対して、どういうデータサイエンスの教育アプローチが考えられるでしょうか。
松原:ChatGPTを例にすると、ChatGPTに何か質問をしてその答えに対して「これは正しい回答ですか?どこか間違っている部分があったら調べてそれがどこかを指摘しなさい」という課題を出すのは有効だと思います。つまりAIが出力したものに対するファクトチェックをさせるわけです。おそらく学生はネットで調べると思いますが、ネットで出てきた情報の正誤を色々な根拠から推測して判断する能力は、これからの時代ますます重要になると思います。それを学ぶための勉強道具にはChatGPTは手頃に使えるかもしれません。
何か厳密なプログラムを書いたり統計処理をするのは理系の専門家の役割かもしれませんが、文系・理系問わず、データに対するリテラシーとしてツールから出力されたものの真偽や精度、確度などを評価する勘を育成することは重要だと思います。卒業後にどの分野に進むにしろ、データが大きな役割を占める世の中になりますから、そうした感覚が養われていないと何かしらの躓きや失敗につながることにもなりかねません。データは故意であれ過失であれ、変な処理をすることで好き勝手な結論も出せてしまいます。ですから、それを見破るリテラシーを持つことは生きて行く上で必要なことだと思います。
(Writer:高橋ミレイ)
